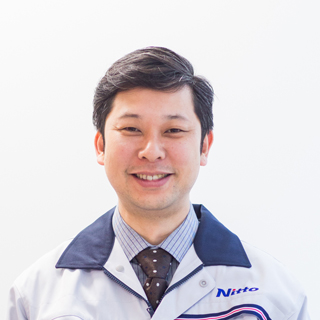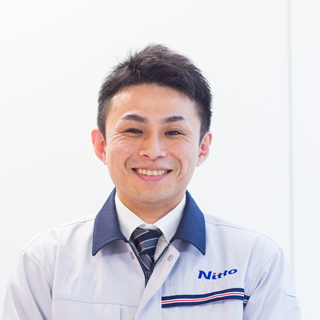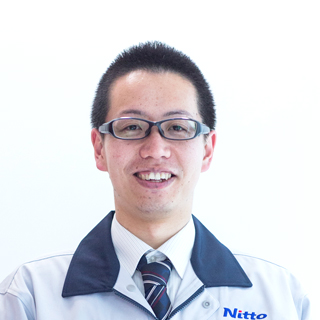STORY

 企画 星の情熱
企画 星の情熱
かんたんに諦めない。
諦めたくない。
ふせんとしてノートに貼りつけられるメモパッドがあったらいいのでは――。エディターズメモは、こんなシンプルな発想から生まれた。ふせんとメモの両方の機能を兼ね備えた文具は市場にはなかった。「おもしろそうじゃないか」社内の企画会議にエントリーすると、すぐにGOが出た。当時入社2年目の星貴代美にとって、ゼロから立ち上げた初めての商品である。
星には、実現したいイメージがあった。サラサラした書き心地の上質紙で、ペンで書いてもにじまない。メモしたものを、そのままノートにもパソコンにも貼れる。粘着部分にゴミがつかないよう厚手の表紙で覆われ、机の上に置いたときの佇まいも美しい。これらのイメージを開発担当者に伝え、製品化がスタートした。
2ヶ月後、東京本社の星のもとに、豊橋工場から1回目の試作品が届く。自分のアイデアが初めて形になるのを見るのは、ワクワクする瞬間だ。だが、そんな高揚感は、すぐ落胆に変わった。メモパッドの紙の部分が大きく反り返っていたのだ。粘着力が強すぎるためか、剝がした後の糊残りも気になった。その後、何度もつくり直してもらったが、なかなか思うような試作品はあがってこない。豊橋工場に常勤する開発担当者とテレビ会議でやり取りするのももどかしかった。
ある時、思い切って豊橋の試作現場を訪れた。自分の思いを直接伝えようと思ったのだ。実際に現場を見てみて、分かったこともある。複雑な製造工程に四苦八苦しながらも、開発と技術の担当者は、紙の反りをなくすために様々な対策を試みていた。
星は、もう少しフラットになる方法を検討してみてほしいと頼んだ。すると開発担当者は、間髪入れずにこう言った。
「そんなの、無理じゃんね」
先輩社員にそう言われたら、以前なら引き下がっていたかもしれない。彼らの言い分ももっともだと納得したかもしれない。でも、この出来上がりには満足していない。今回は言わなきゃ、と星は思った。企画担当の自分が言わなければ、いい商品を世に送り出すことができない。
「STÁLOGY®として、佇まいの美しさはどうしても譲れないんです。もう少し改良をお願いします!」
そう言って頭を下げた。
※所属部署は取材当時のものです。


星の想い
製品コンセプトから
逃げない。
試作品を検証して、どこまでは許せて、どこまではこだわり抜かなければいけないかを判断するのが難しかったです。製品化は社内の様々な立場の人の助けがなければ実現しません。企画担当として製品コンセプトをぶらさないこと、「どうしてこの商品を出したいのか」を説明して社内理解を得ることが大事だと学びました。

 商品開発 手塚の執念
商品開発 手塚の執念
ほんとに出来るのか。
やってやろうじゃないか。
開発担当の手塚洋登が、ふせんの新商品開発と内製化のリーダーを任されたとき、意気込みよりも不安のほうが大きかった。企画を具現化するためのグランドデザインを描き、発売までもっていくのが開発担当の仕事だが、それまでふせんの生産はパートナー企業に委託していたため、手塚にはもちろん、社内にもふせんを作るための知見もノウハウもなかったのだ。
だからこそ、ふせんの内製化は会社にとって大きな挑戦であり、チャンスだった。ふせんの生産技術を自社で培うことができれば、自社で生産できる製品も増えるだろうし、今後の新製品の開発にも生かせる。プロジェクトにかける会社の期待はうれしい反面、大きなプレッシャーだった。
社内でふせんが作れるのか――。手塚の不安は的中した。手探りで試作してはみたものの、ふせんをめくってノートに貼ると、くりん、と丸まってしまうような代物だった。試作をくり返すうちに問題点は改良されていったが、企画担当の星はなかなか首を縦に振らない。質の高さを求めすぎれば、今度は生産コストに跳ね返ってくる。
「価格とのバランスも考えれば、これくらいで十分だろう?」
こんなに苦労しているのに、こいつは高望みばかりだ。
手塚の口調には苛立ちが混じっていた。
星が求めるものをどう実現していくのか。試作してみて、目標のスペックに適っていなければ、対策を考えて改良を施し、また試作する。技術担当者と二人三脚の日々が続いた。
問題が起きたら、その原因をつかむことが肝要だ。そうはいっても、初めて挑戦する技術なので原因の特定も容易ではない。問題は大量に発生するうえに、大抵は材料や設備、工程など様々な要因が絡んでいた。開発や生産に携わるメンバーを集めて定期的にミーティングを開き、問題点を一つひとつ解決していった。
改善できたときは、安堵が先にきた。問題を克服した達成感や感動は、その後でしみじみと訪れた。手塚が途中であきらめなかったのは、ともに悩み、知恵を絞る仲間がいるからだ。
このプロジェクトは、決して自分ひとりで進めているのではない。
こいつらのためにも頑張らなければ。
仲間の存在が頼もしかった。
※所属部署は取材当時のものです。


手塚の想い
新規プロジェクトは、
旗振り役がキーマン。
ふせん作りの技術を社内に取り入れて、今後展開される製品に活用していきたいというのは、開発に関わるメンバー全員の思い。プロジェクトの旗振り役は私でしたが、たんに指示するだけでなく、自分もみんなと一緒に汗をかく。そういうスタンスで取り組みました。

 技術開発 児島の苦悩
技術開発 児島の苦悩
応援してくれる人たちがいる。
負けるもんか。
技術担当の児島壮信は、もう1ヶ月も、なかなか改善されない紙の反りと格闘していた。原因は何なのか、おおよその見当はついていた。ふせんには、貼っても剥がれるようにするために剥離剤が塗ってあるが、その剥離剤が関係しているのではと児島は考えた。剥離剤を塗る量、面積、厚さを様々に変えて試してみた。
ふせんを作った直後はうまい具合に平らになっても、時間が経つにつれて反りが出ることもある。製品が店頭に並んだ後にそんな現象が起きたら、目も当てられない。初期の段階と時間が経過した段階のいくつかのパターンで、温度や湿度などの条件を変えて試験することも忘れなかった。
技術の仕事は、製品化に必要な技術の開発をすることだ。児島は印刷のインク、剥離剤、粘着剤など材料の選定や配合設計、星が要求する性能を満たすための生産条件の検討を担当した。
プロジェクトへは上司の指示で参加した。会社が内製化を模索していることは聞いていたし、内製化は進めていくべきだと自分も思っている。ただ、その大役が自分に降ってくるとは夢にも思ってなかった。当時入社3年目の児島には、正直言って荷が重かった。
もし、自分ひとりだったら逃げ出していたかもしれない。プロジェクトは、児島が所属する開発部だけでなく、事業部・製造部・生産技術グループ・調達グループ・品質保証部など社内の様々な部署との連携によって進められている。自分がつまずけば、他部署の工程にも迷惑がかかってしまう。できるだけ早く技術と生産方法を確立させ、製造部での量産に引き継ぐのも児島の役目だった。
プロジェクトを通して、社内でたくさんの人と出会い、知り合いも増えた。これも児島には初めての経験だった。試作に悪戦苦闘していると、他部署からも先輩社員が心配して見に来てくれた。自分のことを気にかけて、応援してくれる人たちのためにも、製品化と内製化を何としても実現したかった。
※所属部署は取材当時のものです。


児島の想い
部署の敷居を超えた、
絆が生まれた。
量産に向けて製造部の今泉さんと密にやり取りする機会がありました。生産の現場に自分も立ってみて、ものづくりの大変さを経験し、これまで開発目線でしか見ていなかったなと反省しました。相手の立場に立ったうえで、目標達成のためにどうコミュニケーションを取っていくのか。新たな視点を持てたのは大きな収穫だったと思います。

 生産技術 鈴木の平静
生産技術 鈴木の平静
難題だなあ。
ま、いっか。
製品化の目途が立った頃、生産技術の鈴木基紘がプロジェクトに招集された。量産に向けて、安定的かつ効率的に生産するための設備の設計を任されたのだ。新製品の場合、製品化のための技術が確立しても、安定的に生産ができなければ、製品を世に出すことはできない。いかに不良品を少なく、効率よく生産でき、製造現場の人たちにとっても作業しやすい設備を組み立てられるか。このプロジェクトの成否は、鈴木の肩にかかっていたと言ってもいい。
鈴木が担当したのは、製造の最終工程にあたる、印刷した紙を重ねてふせんの形状に型抜きする「積層/打ち抜き機」の設計だった。これはふせんの製造工程のなかで、最も高度な技術が要求される部分だ。エディターズメモは、60枚の紙の積層で成っている。これを印刷部分に寸分のズレも生じないように重ね合わせ、正確に切断しなければならない。
ハードルは技術面だけではなかった。児島が担当する技術面の仕様や生産条件での試行錯誤が、この段階でもまだ続いていた。通常は仕様が固まってから設備設計を始めるが、製品の発売日から逆算すると、技術開発と並行して設備設計を進めなければならなかったのだ。仕様が変更されるたびに、何百枚も描いた図面が一瞬でパーになった。
まぁ、しょうがないな――。
どうにもならないことには執着せず、サッサと前を向く。マイペースで飄々とした性格が、鈴木の取り柄でもある。設計を進めていくなかで、どうにか形になりそうだという手ごたえも感じ始めていた。
ところが、いざ設備を組み立てて生産を始めると、重ねた紙の印刷位置に想定以上のズレが出た。設計で意図したとおりに紙が重なっていないのだ。発売日は迫っている。普段はあまり動じない鈴木の額にも汗が流れた。
プロジェクトの初期の頃、鈴木は試作現場を訪れていた星に何度か会っていた。現場にまで足を運ぶ企画担当は珍しく、企画に相当思い入れがあるんだな、と強く印象に残っていた。
この企画にかける彼女の思いに何とかして応えたい。
鈴木はシャツの袖をめくり、ふたたび図面に向き合った。
※所属部署は取材当時のものです。


鈴木の想い
ちゃんとできた。
うん、よかったです。
僕が設計したのは最終工程ですが、その前工程に関わる粘着剤の選定や配合の試行錯誤が続くなかで、最終工程の設計を平行して進めなければならないのは大変でした。ただそれも、決められたスケジュールで内製化を目指すには仕方がないのかなと。設計するときは、製造部の人がなるべく作業しやすい形になるよう気をつけています。

 製造 今泉の試行
製造 今泉の試行
不安だ。でもこの機械、
使いこなしてみせる。
打ち抜き工程を経て、完成品一歩手前の状態となったメモパッドを見て、製造担当の今泉勝は頭を抱え込んだ。60枚の積層のうち、1枚だけ印刷位置がズレているのだ。
なぜズレてしまうのだろう? しかも1枚だけ?
1枚でもズレれば、残りの59枚に問題がなくても不良品である。
不具合が生じたら、原因と思われることに一つ一つ対策を講じていくしかない。それでもズレは直らず、なかなか原因を特定できなかった。機械を動かせば動かすほど、不良品の山ができていく。今泉は絶望的な気持ちになった。
機械の問題か、それともセッティングの問題だろうか。設計担当の鈴木とリーダーの手塚にも相談した。機械の内部を見てみると、紙が何かに引っかかって、うまく引っ張られていないことが原因ではないかと見当がついた。
いくつもの方法を試してようやく改善されることもあれば、紙のセッティングの位置を微調整するだけで改善できることもある。少しの工夫で道が開けるから、試行錯誤はおもしろいと今泉は思う。
現場では依然、不具合に対処しながら生産する綱渡りの状態が続いていた。発売日はもう目の前だ。リーダーの手塚は、休日も返上して製造現場の今泉を手伝った。すると、それまで一緒に頑張ってきた仲間たちが、「自分たちも手伝います」と休日出勤を買って出てくれた。
あともう少し。これで乗り越えられるかもしれない――。
※所属部署は取材当時のものです。


今泉の想い
苦労したセッティングで製品ができた。うれしかった。
発売後、お店で商品を見たときはうれしかったですけど、半分は心配でしたね。印刷がズレていないかな、とつい見てしまいます(笑)製品が世に出た今、生産の安定化と効率化をさらに進めていくのが僕たちの次のチャレンジです。

 エピローグ
エピローグ
言い合ったからこそ、
いいものができた。
紙だけの状態だったメモパッドに、黄色や水色、赤色の表紙が巻かれ、エディターズメモ®が完成した。完成した商品を手に取って、手塚は目を見張った。企画担当の星がこだわり続けてきた佇まいの美しさは、これだったのか、と思った。
この商品、かっこいいなぁ。
星は東京・代官山にあるSTÁLOGY®直営店にいた。エディターズメモ®の並べ方を販売員に指示したり、POPを用意するためだ。
「こういうのが欲しかったんだよね」エディターズメモ®を購入したお客さまの言葉がうれしかった。
手塚も商品が発売されてすぐ、文具売り場に見に行った。
「あった!」
エディターズメモ®が目立つように商品をこっそりと動かし、少し離れた場所からお客さまの様子を見守った。
製品化の過程でメンバーとは激しく議論した。あれだけ言い合ったから、お客さまが求めてくださる商品ができた。これからも簡単に妥協せず、仲間を信じながら一丸となって課題に取り組んでいこう。そうすればどんな困難も乗り越えられる。手塚はそう思っている。